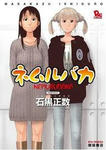
ネムルバカ / 石黒正数
「それでも町は廻っている」で知られる石黒正数の「ネムルバカ」を読んだ。
「それでも町は廻っている」は読んだことないがギャグ漫画だということは知っている。なので「ネムルバカ」もギャグ漫画なのだと思って読んだのだが、これがギャグ漫画には思えなかった。
自分には人間ドラマかはたまたドキュメンタリーか、個人的に最も近かったのはホラーかな…。
大学の女子寮で暮らす二人。センパイは大学に通いながらインディーズバンドを組んでいる。いつの日かメジャーデビューすることを望み日々切磋琢磨している。
一方コウハイはなんとはなしに一日を過ごしている。夢はなくて一日をなんとはなしに過ごしている。
自由で夢に溢れ、だが現実を少しずつ見えるようになってきた"大学生"の日常をユーモアと痛さをもって描いた作品。
とにかく自分の立場上この作品はかなり痛かった。
痛いといっても引くほうではなくて心に刺さってくる痛さ。
自分の現実が夢があるコウハイのような者なので登場人物たちの現実や夢に対するセリフがグサグサと刺さってきた。
例えば...
「妄想ってのは妄想の中でウソを演じてる限り絶対実現することはありえないの」
「デカすぎる目標を立てるのは何も出来なかった時のカモフラージュかもしれないけど、やりたいことがないって公言するのも何も出来なかった時の言い訳なんじゃね?」
などのセリフも骨身に沁みたが、強烈にインパクトに残ったのが「駄サイクル」
「駄サイクル ― 私の造語 ぐるぐる廻り続けるだけで一歩も前進しない駄目なサイクルのこと 輪の中で需要と供給が成立しちゃってるんだよ 自称ア~チストが何人か集まってそいつら同士で見る→ホメる→作る→ホメられるを繰り返しているんだ それはそれで自己顕示欲を満たすための完成された空間なんだよ」
「で 自称ア~チストってのは常々やってて楽しいと思える程度の練習はするが本当に身になる苦しい修行はツラいからせず・・・一方的に発表できる個展はするが正式に裁きを受けるコンペやコンクールは身の程知るのが怖いから出ず・・・馴れ合いの中で自分が才能あるア~チストだと錯覚していく・・・駄サイクルの輪は自称ア~チストに限らず色んな形でどこにでもある…たぶんここにも―」
もう見ていられなくなりそうだった。
まるで自分のことを言っているようで目を逸らしたくなった。
自分の場合は自称ア~チストな仲間を作っていないが駄サイクルの輪には確実に嵌っている。
やってて楽しい程度の練習はするけど苦しい修行からは逃げている。
実際理解している。努力をしなければ先には進めないこと。なのにその努力ができていない。
難しい…。
自分のことばかり書いてしまったが「ネムルバカ」自体は体裁としてはギャグマンガに分類されるので痛い部分だけではなくて笑えるところもいくつもある。
そんなギャグ漫画な日常が描かれている作品のほんの数ページにはっとさせられるものがあるから怖いのだけれど…。
しかし、こんな風に魅力的に日常を描くのなら「それでも町は廻っている」も気になるなぁ。
PR








