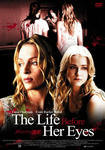
THE LIFE BEFORE HER EYES(邦題:ダイアナの選択)
2008年 アメリカ 90分
監督:ヴァディム・パールマン
製作:ヴァディム・パールマン、エイメ・ペロンネ、アンソニー・カタガス
製作総指揮:トッド・ワグナー、マーク・キューバン、マーク・バタン
原作:ローラ・カジシュキー『春に葬られた光』
脚本:エミール・スターン
撮影:パヴェル・エデルマン
プロダクションデザイン:マイア・ジェイヴァン
衣装デザイン:ハラ・バーメット
編集:デヴィッド・バクスター
音楽:ジェームズ・ホーナー
出演:ユマ・サーマン、エヴァン・レイチェル・ウッド、エヴァ・アムリ、オスカー・アイザック、ガブリエル・ブレナン、ブレット・カレン、ジャック・ギルピン、モリー・プライス、ナタリー・ポールディング
ダイアナは高校時代、モーリーンといつも一緒だった。2人はプライベートなことまで何でも話せる親友だった。
その日もいつものように始まった。
授業前に化粧を直そうと2人はトイレに入る。
そこで話していると、外が騒がしい。叫び声に…そして銃声。
2人は近づく足音に動けずにいると、トイレにクラスメイトのマイケルがサブマシンガンを担いで入ってくる。
「どちらを殺すか選べ」
マイケルはダイアナとモーリーンにそう言うとサブマシンガンを構えた。
モーリーンは「私を殺して…」と言う。
だが、ダイアナはモーリーンのように自分を殺してとは言えなかった。
果たして、ダイアナはどういった選択をしたのか…。
解釈がとても難しい映画だった。
この映画はこういうことを伝えたいのだ! という断定はこの映画においてすることはできないだろう。
映画は高校時代のダイアナと大人になったダイアナ(?)の視点で語られる。
一面的にはダイアナの代わりにモーリーンが死んでダイアナは過去の選択を悔いているように見える。
だが、ラストで語られる事実はそれとはまったく違っていた。
ラストには自分の中で2通りの解釈ができた。
1つ目は映画の大部分で描かれていくように殺されたのはモーリーンでダイアナは当時の選択を悔いている。
子供ができたが、その子供は実は事件のショックによる妄想の産物であったということ。
ダイアナの選択は極限状態では決して間違った選択ではないのだが、それでも当事者には大きな後悔を残してしまった。
選択をしなかったことへの後悔と苦痛。
2つ目はラストまでに描かれていく描写が実はダイアナの妄想であったという解釈。
人は死ぬ間際に走馬灯のように過去の思い出をフラッシュバックさせると言われているが、それが過去に見聞きしたまったく関係のない点(高校時代、町で見かけた男が妄想の中では夫になっている。堕ろした子供につけた名前が妄想の中では実際の子供の名前になっているなど)が憧れていた未来への想いという線になって描かれていたのではないか。
街から出て新しい世界で生きていくことを願っていたダイアナ。まだまだ未来があるダイアナに降りかかった理不尽な死。
ラストで描かれるダイアナの死は自分の後悔や両親、憧れなどをこういう現実であったならばという幻想なのではないだろうか。
恐らく解釈としてしっくりくるのは2つ目の解釈だろう。
だが、個々のセリフや小道具なんかにはまだまだわからないところが多い。
例えば、映画全編を通して『水』が大きなキーワードとなっていること。しかし、その『水』が何を象徴としているのかは納得のいく答えが出せていない。
またダイアナが高校時代、物理の教師に言われた言葉。
・心臓が人間の筋肉で最も強い筋肉である。
・脳には銀河の星よりもずっと多くの細胞がある。
・肉体は72%が水分だ。
この言葉も大きなキーワードだろう。またここでも『水』という言葉が出てきている。
納得のいく答えを得るにはあと何度か観なければいけないだろう。
だが、観るたびに新たな疑問、そして答えも得られそうだ。
悲しくてとても切ない映画だが、それだけではない。
もっと大きなものがある映画だと感じた。
90点/100点
PR








