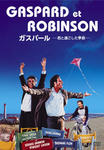
GASPARD ET ROBINSON(ガスパール~君と過ごした季節~)
1990年 フランス 90分
監督:トニー・ガトリフ
製作:マリー・シュラキ
脚本:トニー・ガトリフ、マリー=エレーヌ・リュデル
撮影:ドミニク・シャピュイ
音楽:ミシェル・ルグラン
出演:ジェラール・ダルモン、ヴァンサン・ランドン、シュザンヌ・フロン、ベネディクト・ロワイアン、シャルロット・ジロー
ベン・ハーを観た後に鑑賞した。
あれだけスゴい映画の後に観たのでは霞んで見えてしまうかもしれないなぁ、などと思っていたのだが全然そんなことなかった。
「名前は”ジャンヌ”無一文です。よろしくお願いします」
そのメモを胸に付けられ捨てられた老婆。
眠っているようだ。
眼が覚めると遠くに見慣れた車が見える。
捨てられたのだとそこで悟る。
息子の名を叫び打ちひしがれるジャンヌの眼の前に一台の車が止まる。
「おばあちゃん、どうしたの?」車の男がそう尋ねる。
ジャンヌは胸についたメモを渡すと男は笑ってジャンヌを車に乗せる。
そのまま男の家に招かれ「好きなだけいていいんだよ」とジャンヌに言う。
ジャンヌは安堵と悲しさから眠ってしまう。
男が浜辺を歩いていると同居人の声がする。
「ロバンソン あれは何だ?」
同居人のガスパールはロバンソンに強く当たる。
捨てて来い。
そうロバンソンに言うがロバンソンは困ってる人は助けなくてはいられない性分なのだ。現実を見ろ。お前は甘い。ガスパールにどう言われようともほっとけないのだ。
何を言っても無駄と思ったガスパールはロバンソンに内緒でジャンヌを捨てに行く。しかし、それに気づいたロバンソンはジャンヌを連れ帰ってくる。
ガスパールはこうなったらもう無駄だと判断したのか、その日からロバンソンとガスパール、そしてジャンヌの新たな生活が始まっていく。
ジプシーがこの映画の一つのヒントになっている。
本作に出てくるキャラクターたちは皆ジプシーのような放浪者同然の人たちだ。
ロバンソンは12歳のときから町のベンチで寝ていたという母に捨てられた子。ジャンヌは子供に捨てられている。ガスパールは妻に捨てられた。終盤に出てくるエヴァという女性は男に捨てられたのだろう、娘と二人暮らしだ。
皆、普通の生活には戻れない大きな傷を負っている。
だがロバンソンとガスパールはそれを取り戻そうと二人でレストランを開こうとしている。
そこにジャンヌが入ってくる。
初めは嫌々だったガスパールも共にいるうちにジャンヌに愛情を持ち始める。
それは”家族”のようなものだと思っていたのかもしれない。しかし、家族にはなれない。
そこにロバンソンが一目惚れしたエヴァとその娘が入ったことにより”家族のようだったもの”が”家族”へと変わっていくのだ。
だからガスパールはラストであのような決断をしたのだろう。
もしエヴァの相手がガスパールだったらロバンソンはガスパールがしたような決断をしただろうか?
恐らくしなかっただろう。
それは家族を持っていたガスパールだからこそあのような決断ができたのだ。
寂しく、切ない決断だがガスパールはロバンソンとエヴァ、そしてジャンヌに「いつかきっと君たちが作ったパスタを食べに行く」と置き手紙を残している。
二度と会わない別れではなくて、また会おうという約束だ。
そしてラスト一人歩くガスパールの後ろを毛むくじゃらの汚らしい犬がついてくる。「ついてくるなって言ってるだろ!」「独りにしてくれ」そう叫ぶガスパールの後ろをついてくる犬。
ガスパールは諦めたのか、こっちに来いよと足をポンポンと叩き呼び寄せる。
最後までガスパールは優しかった。
PR








